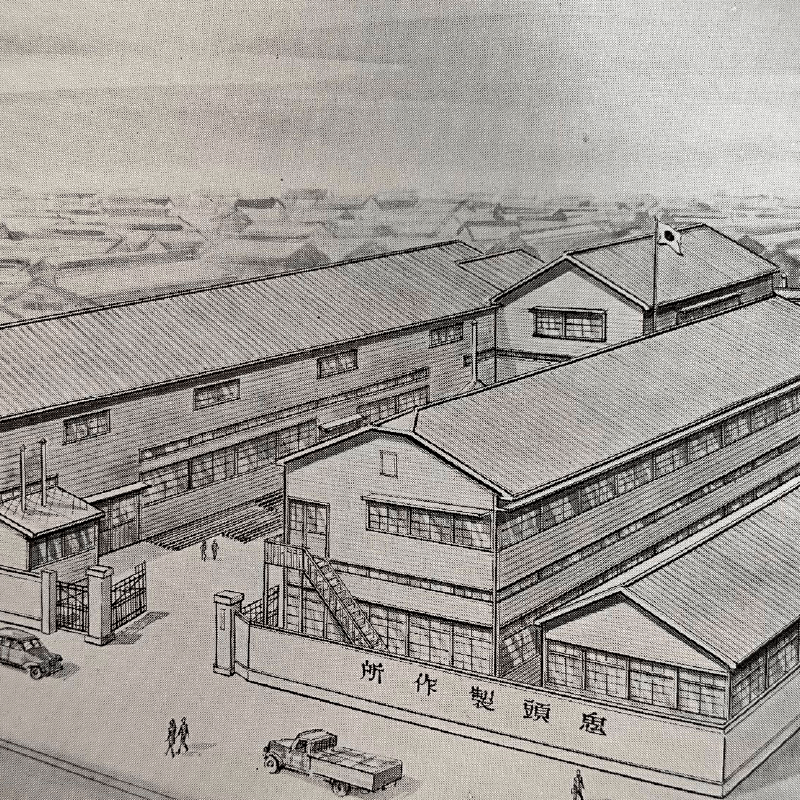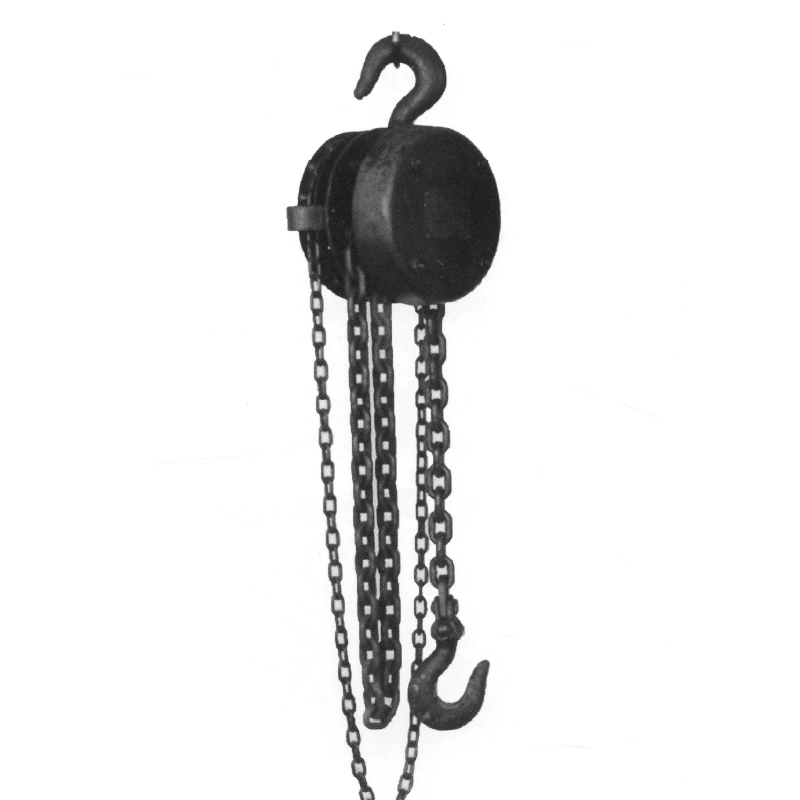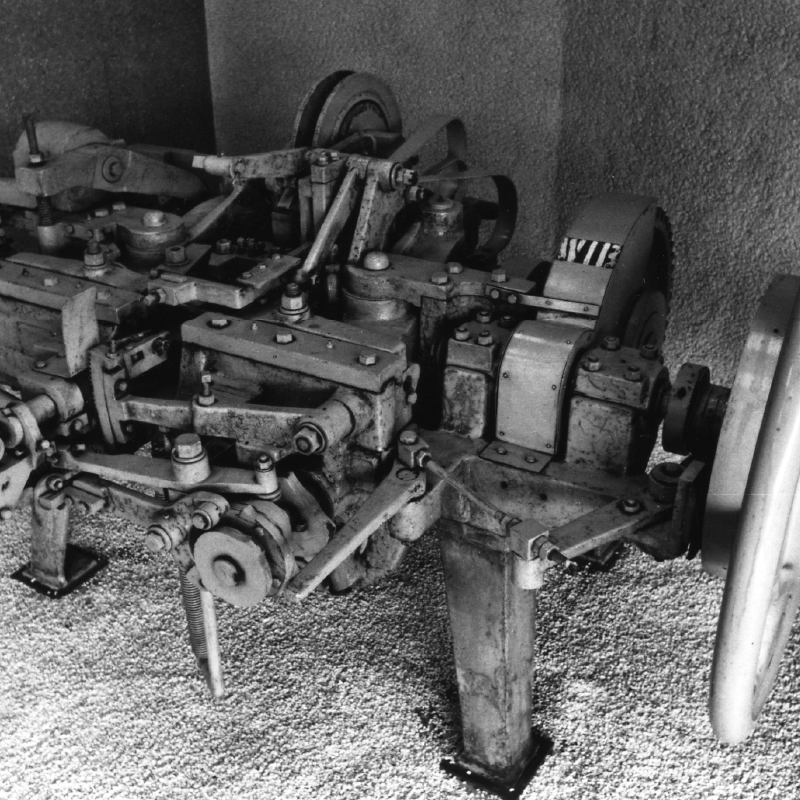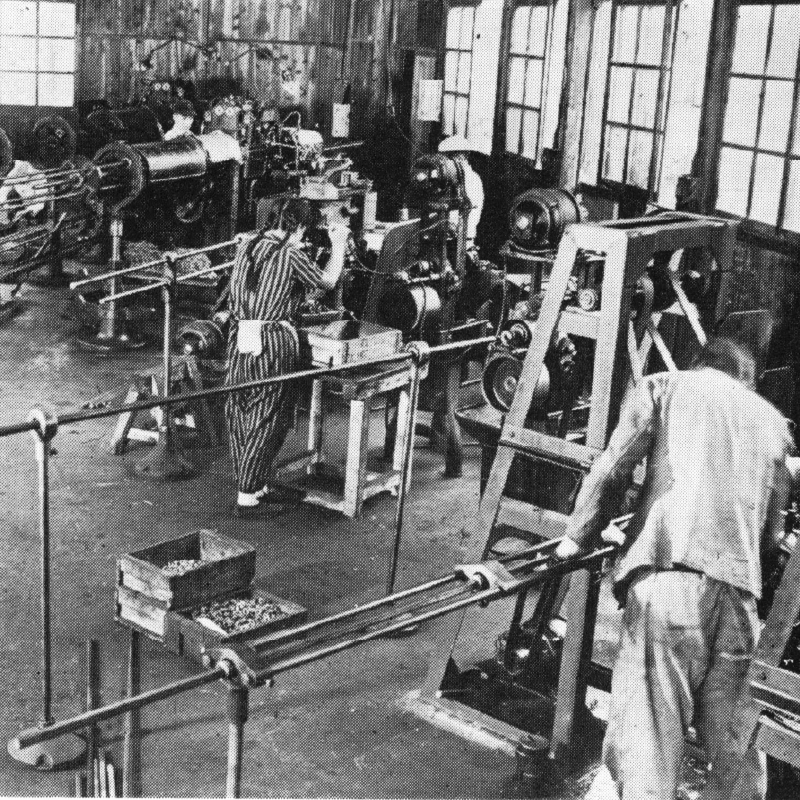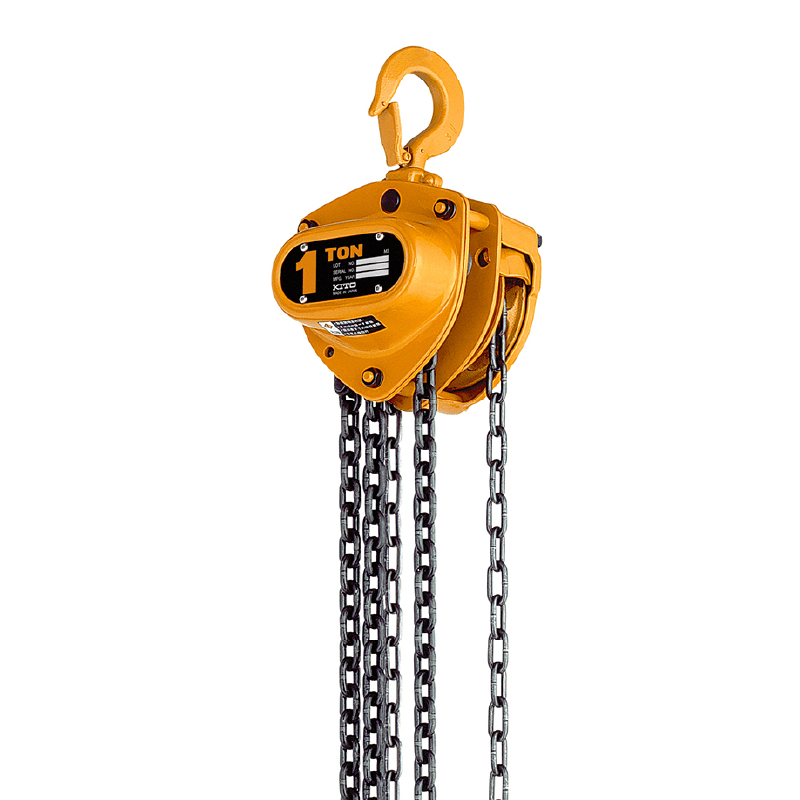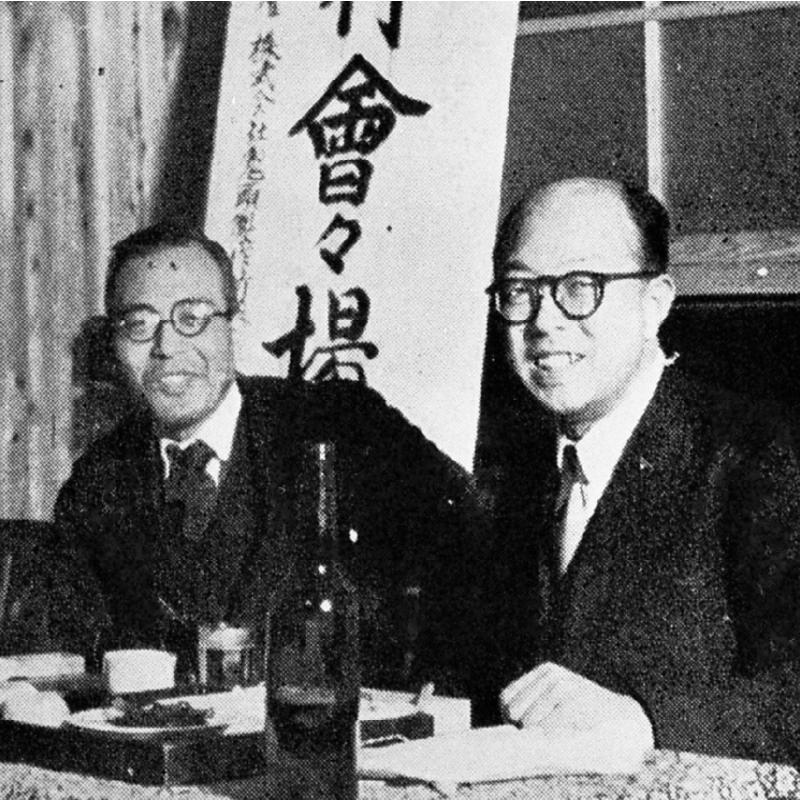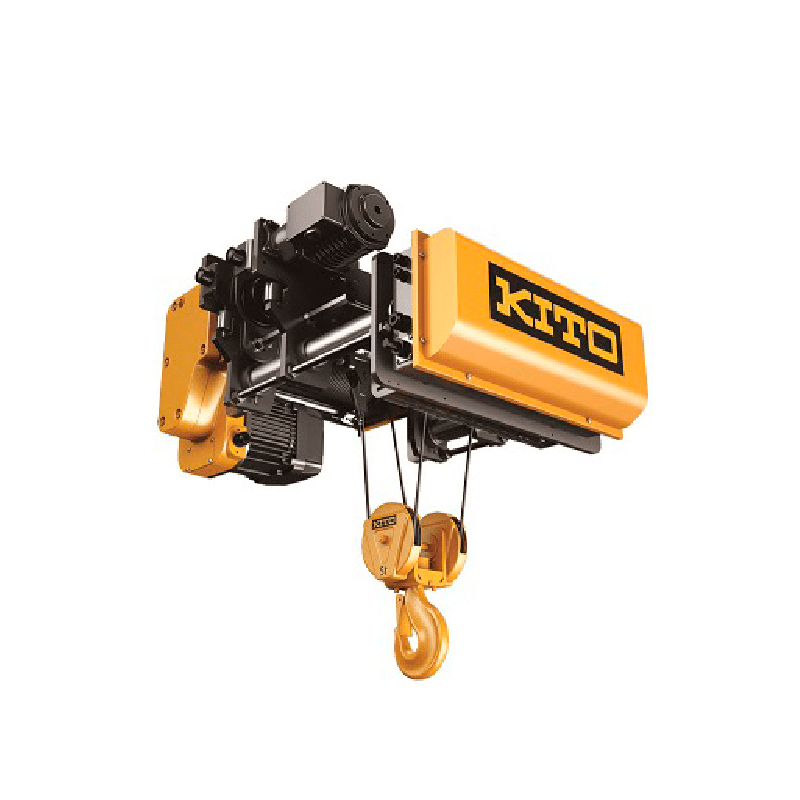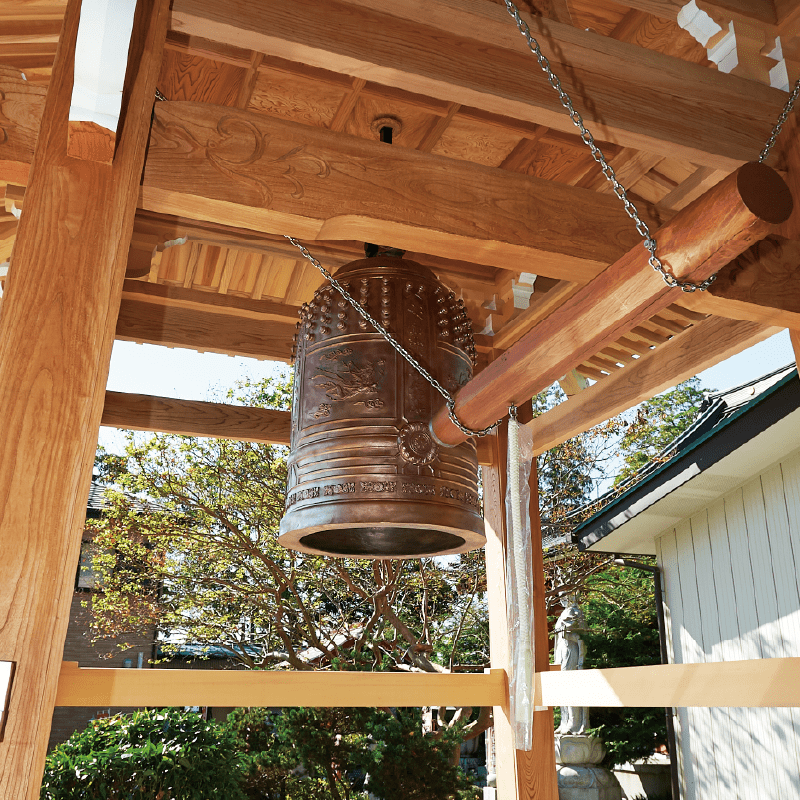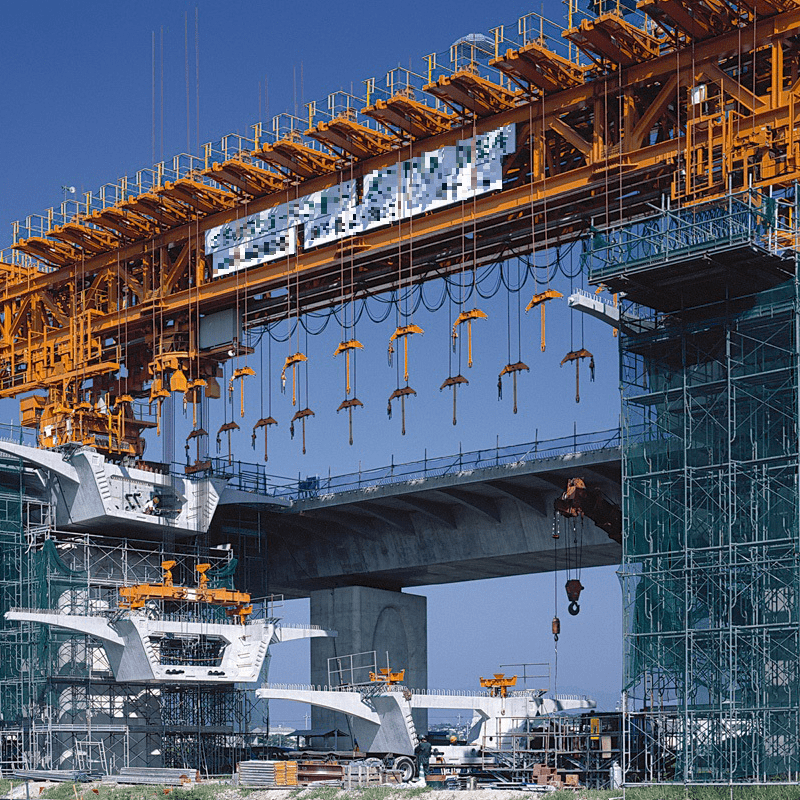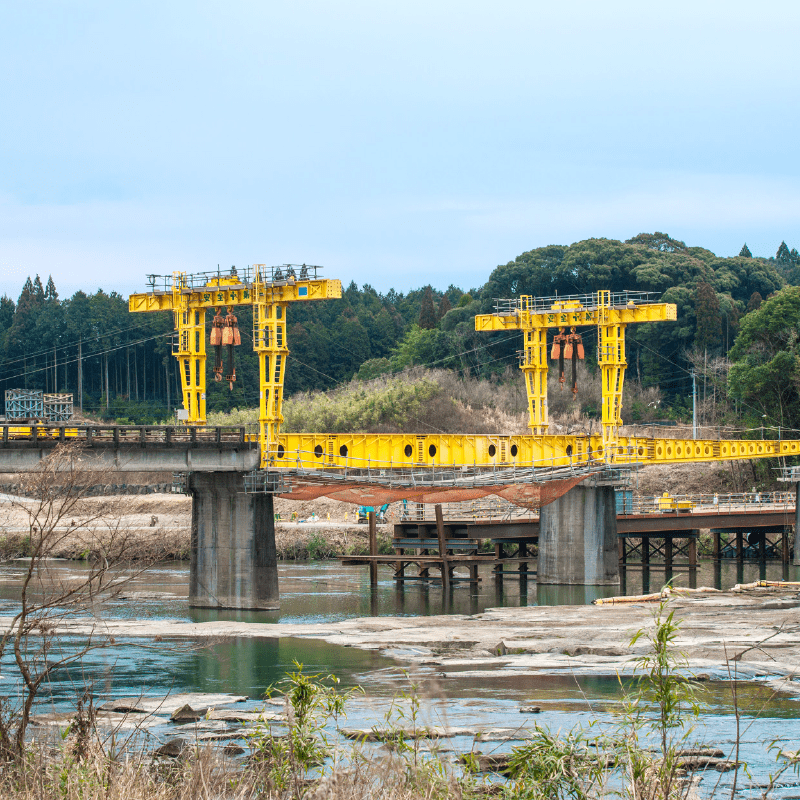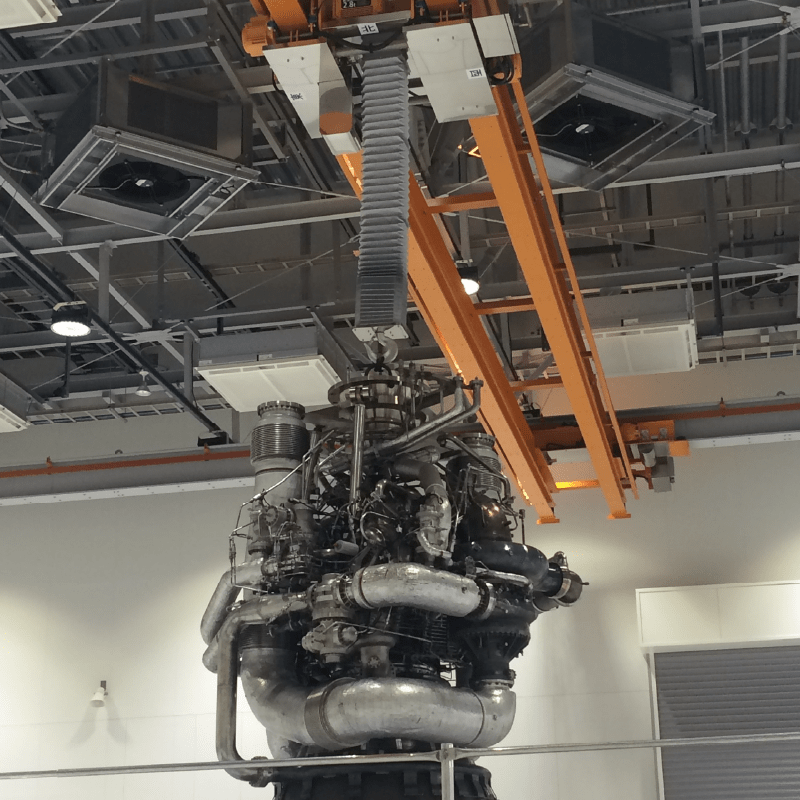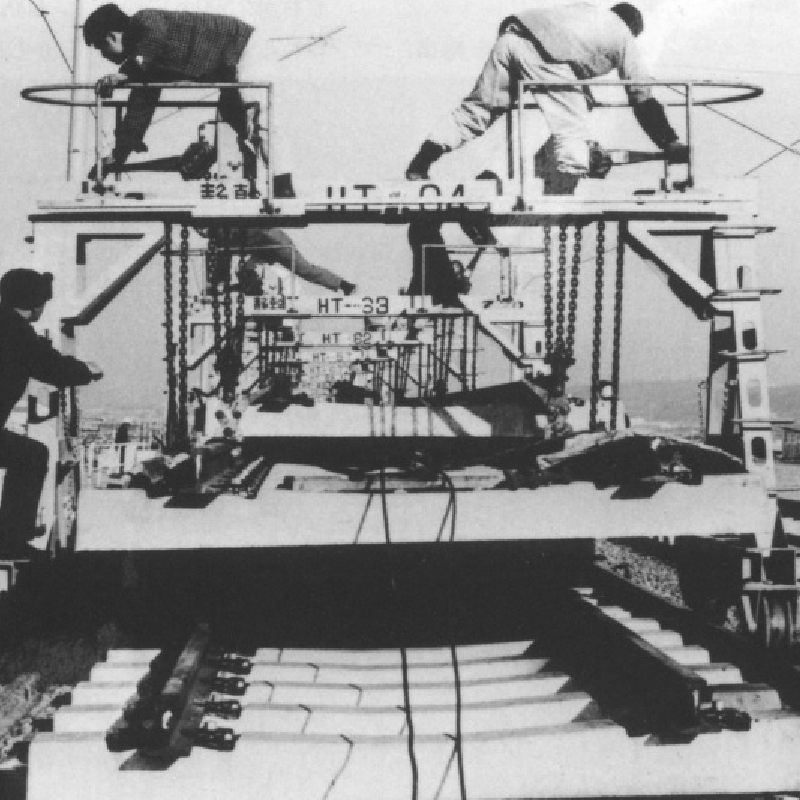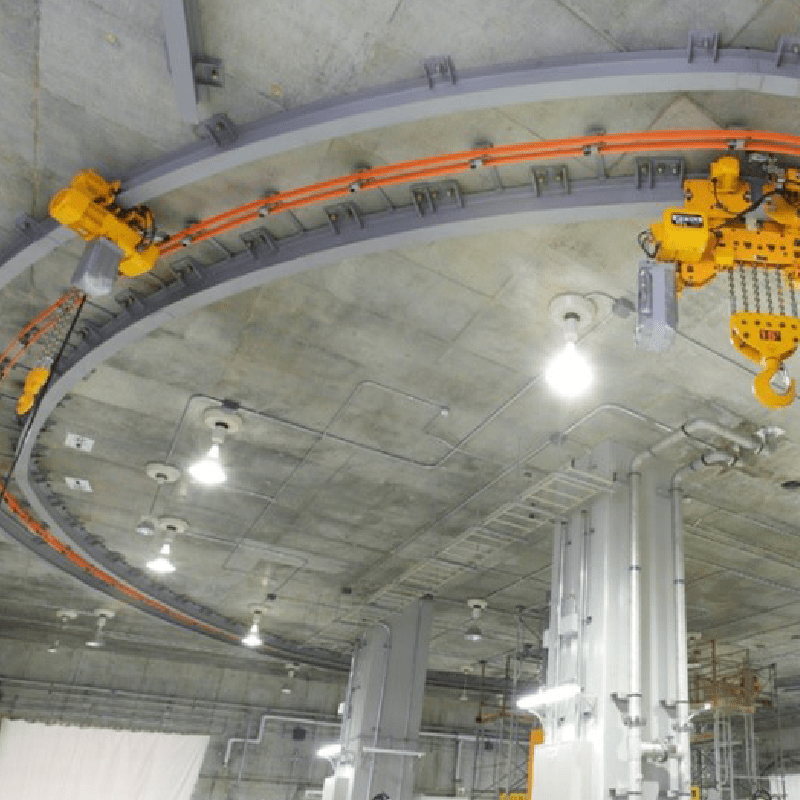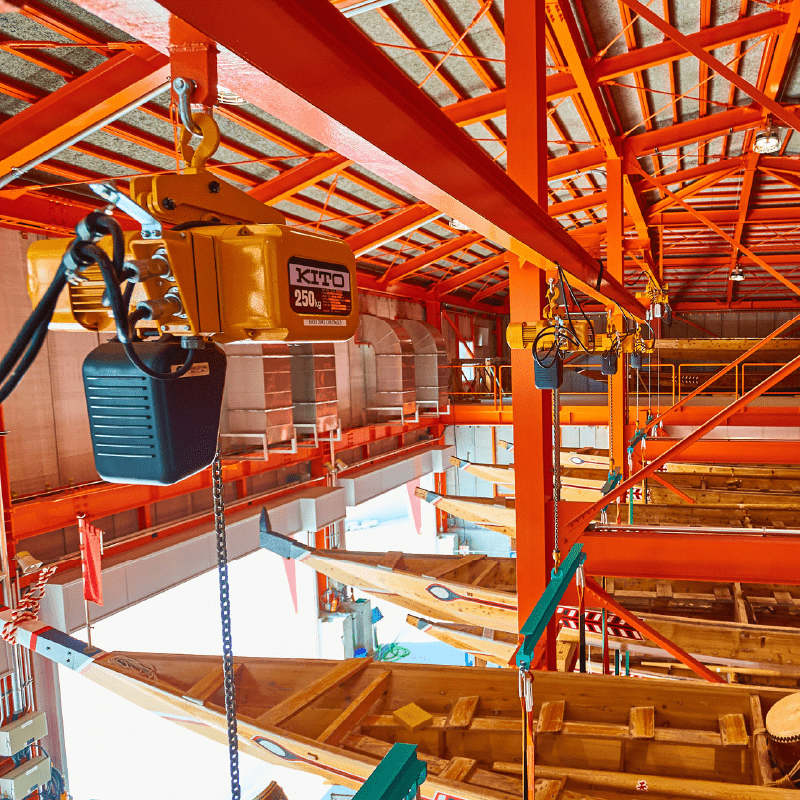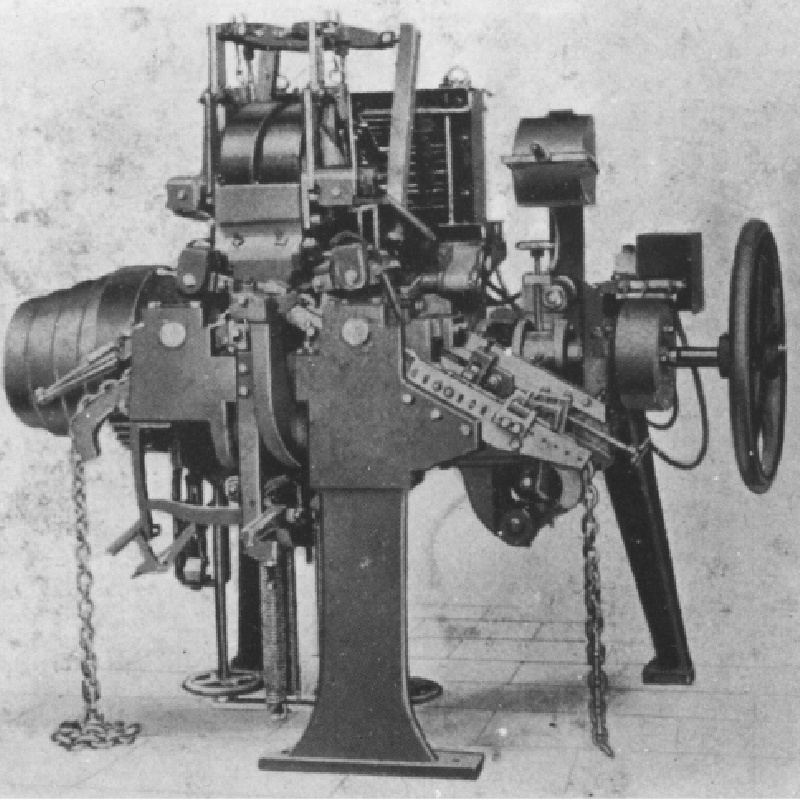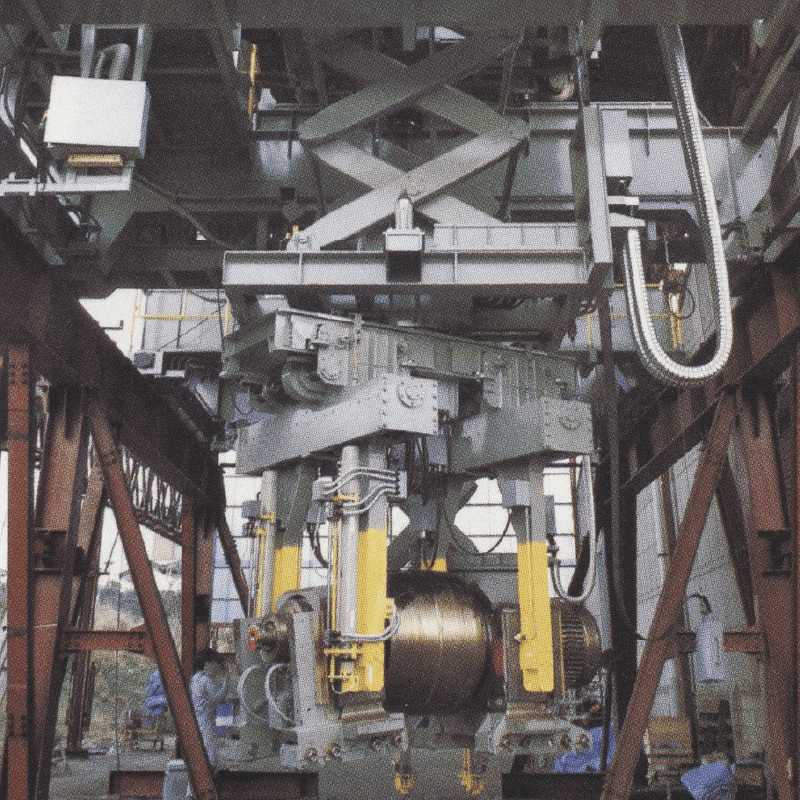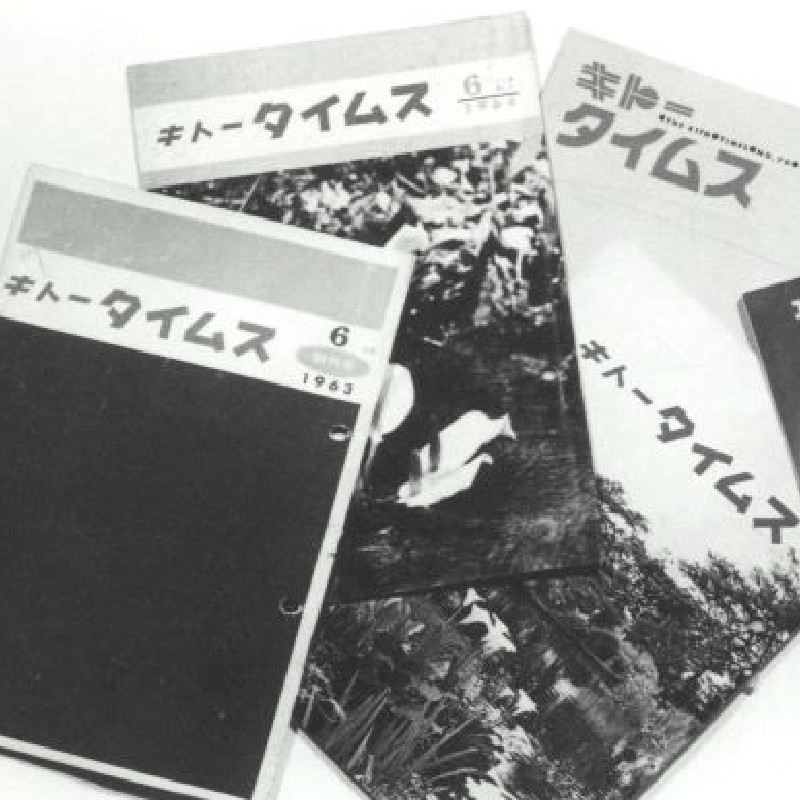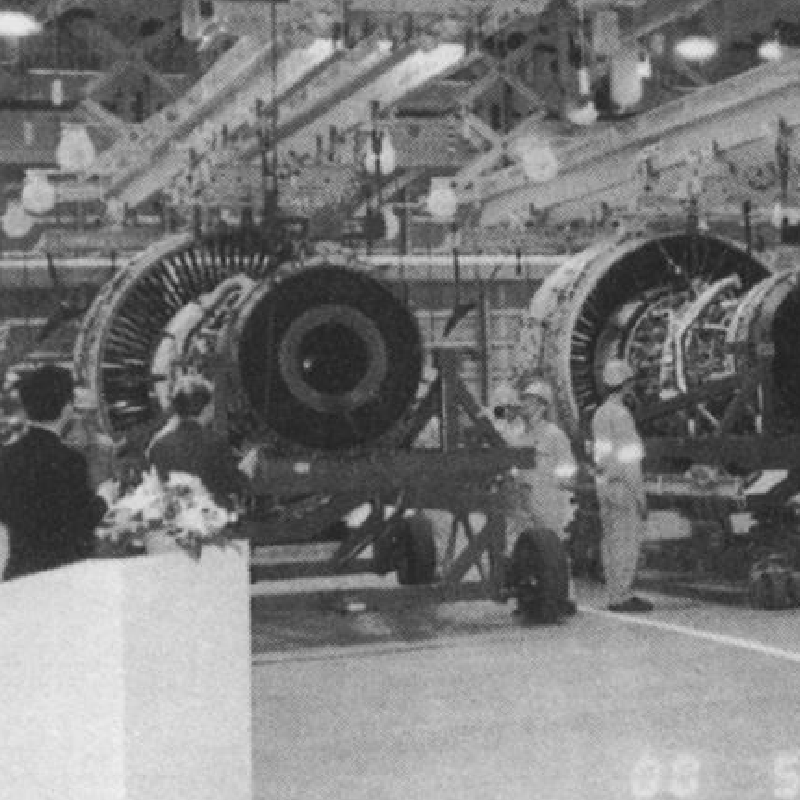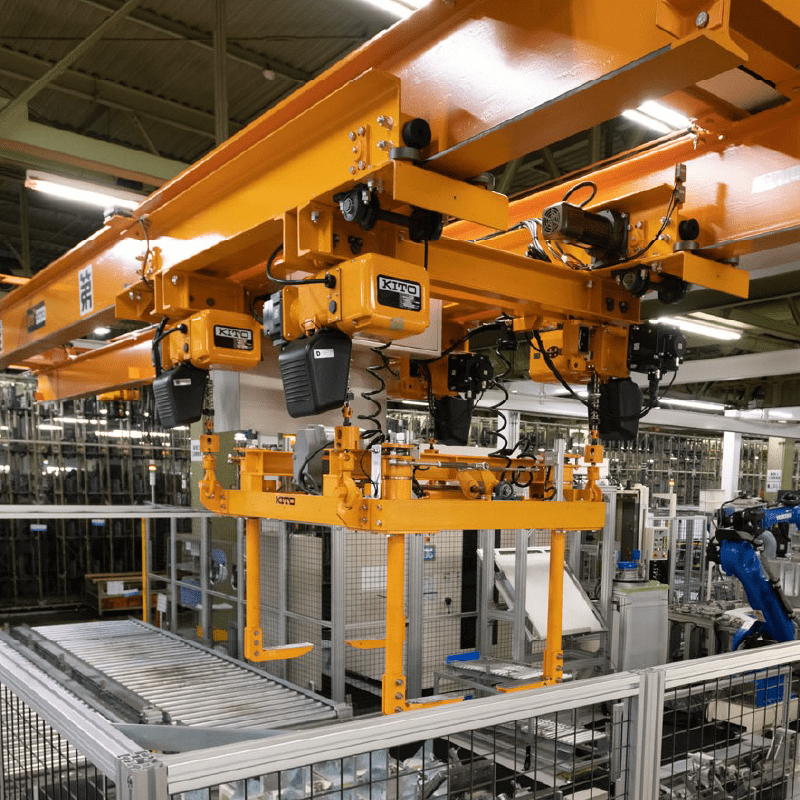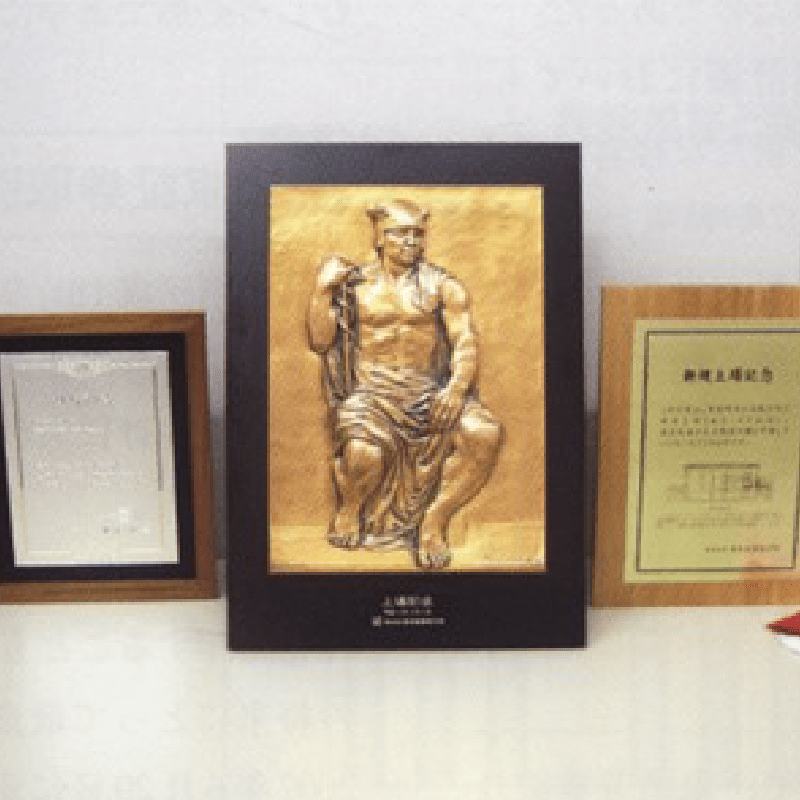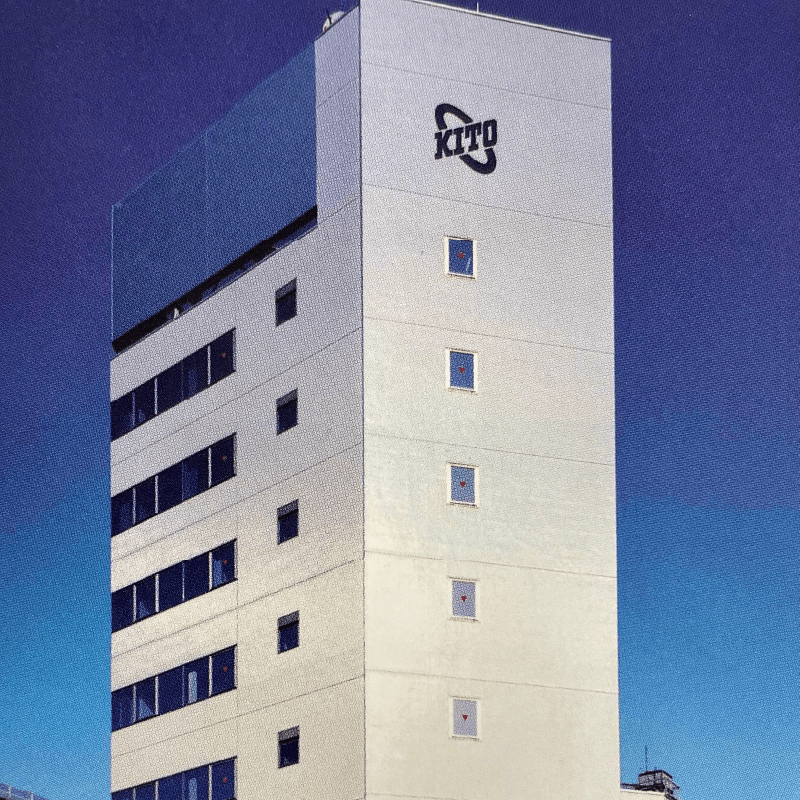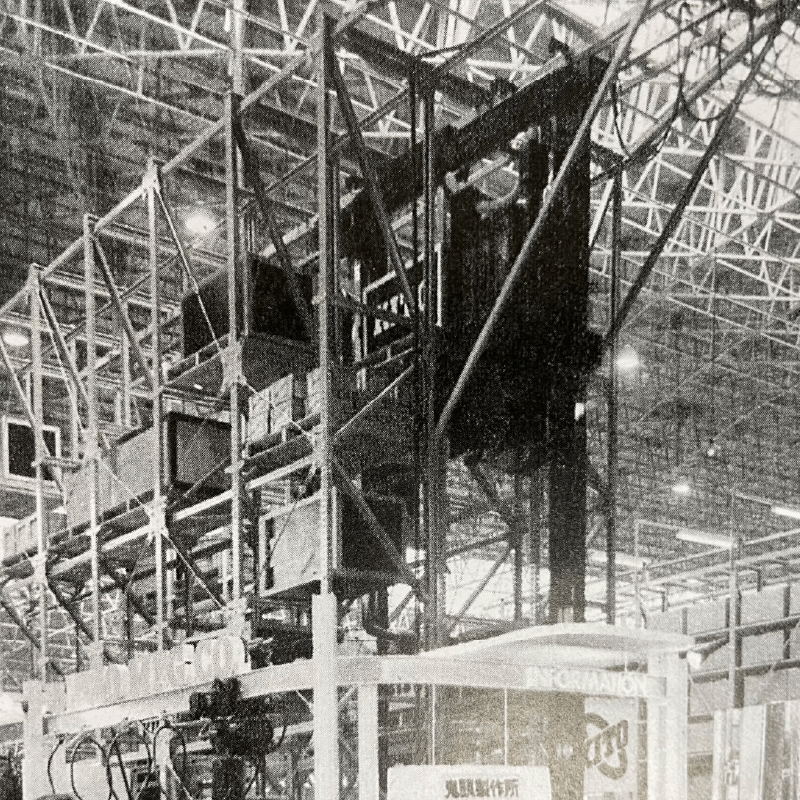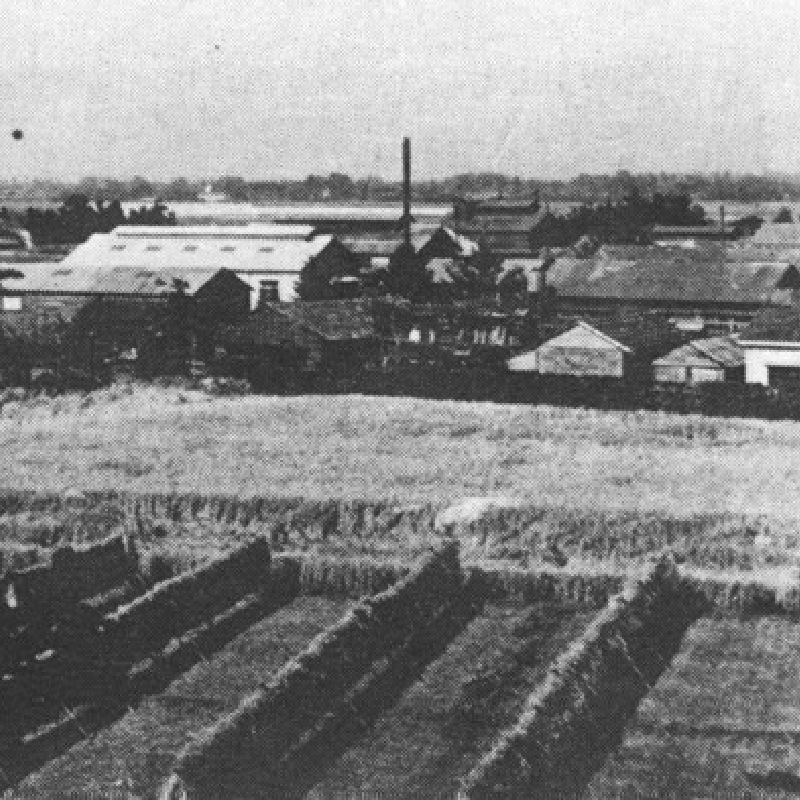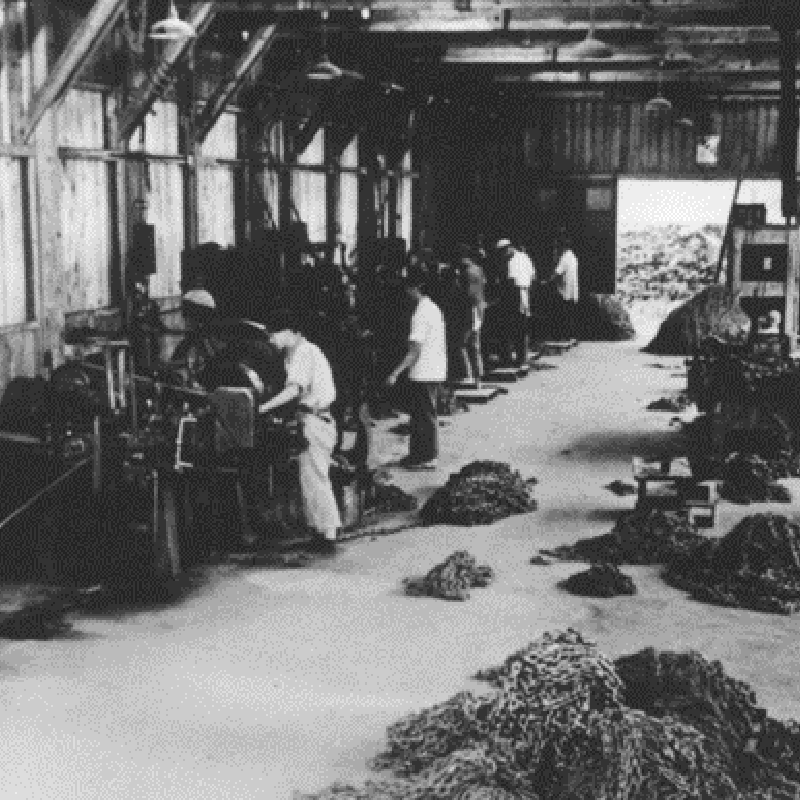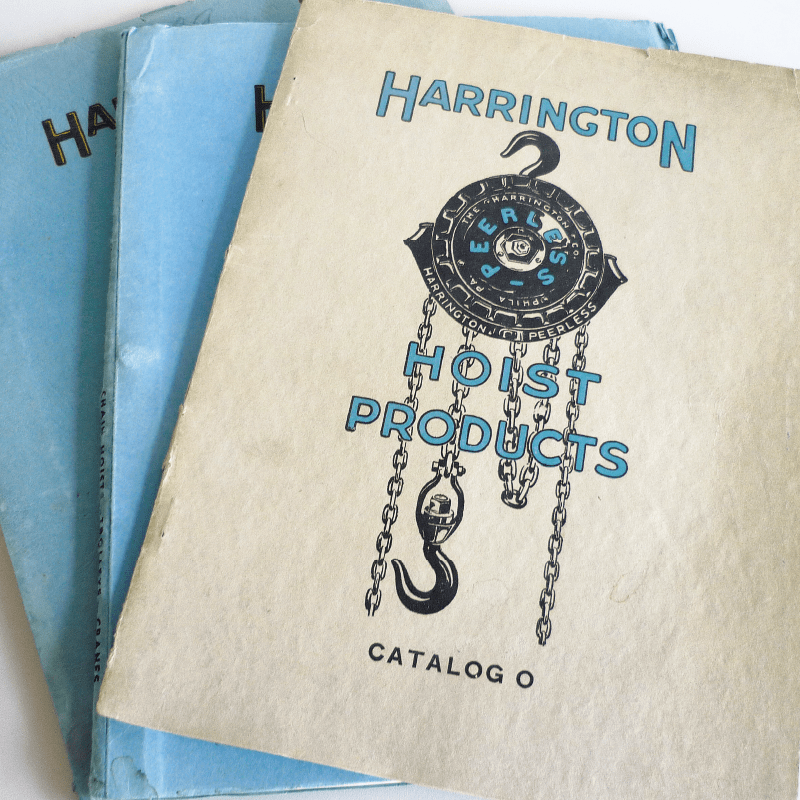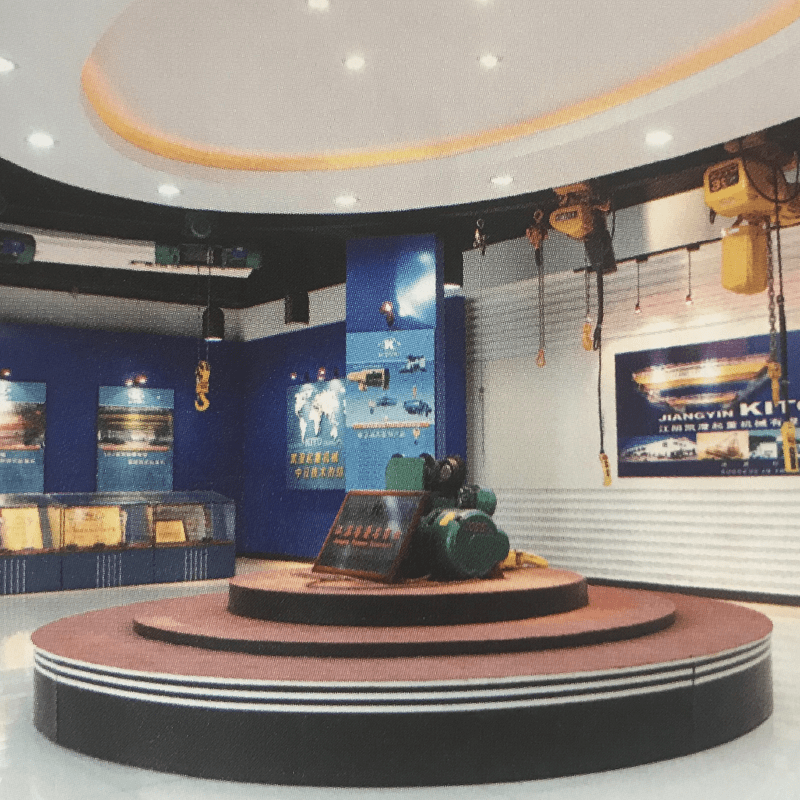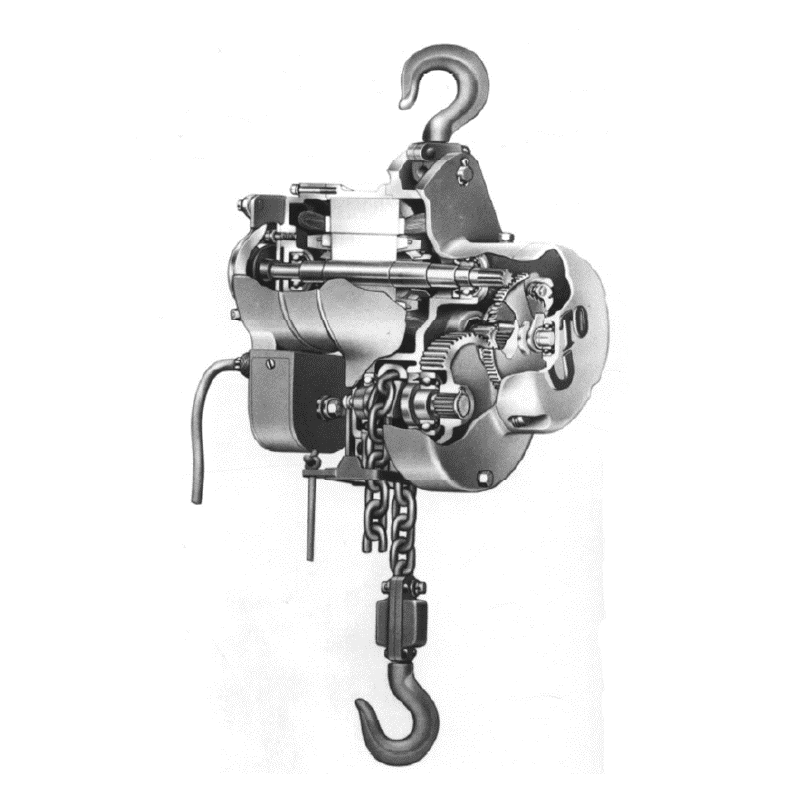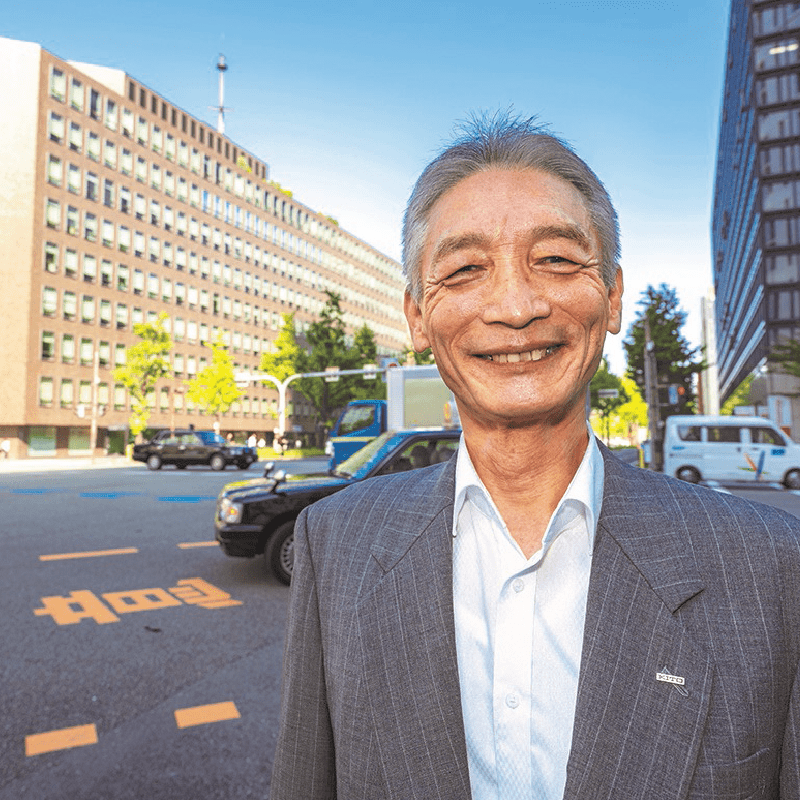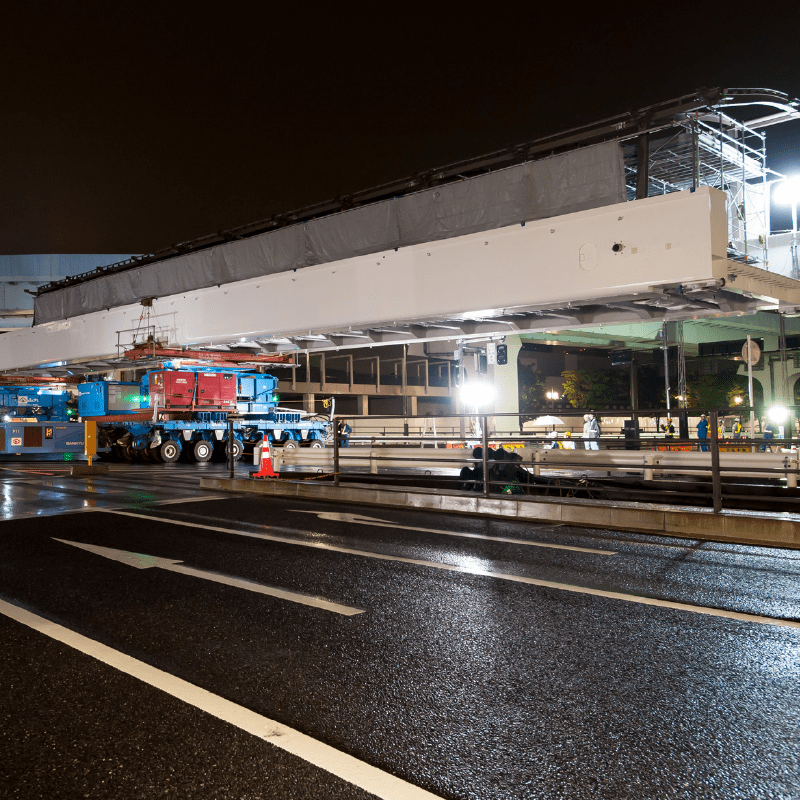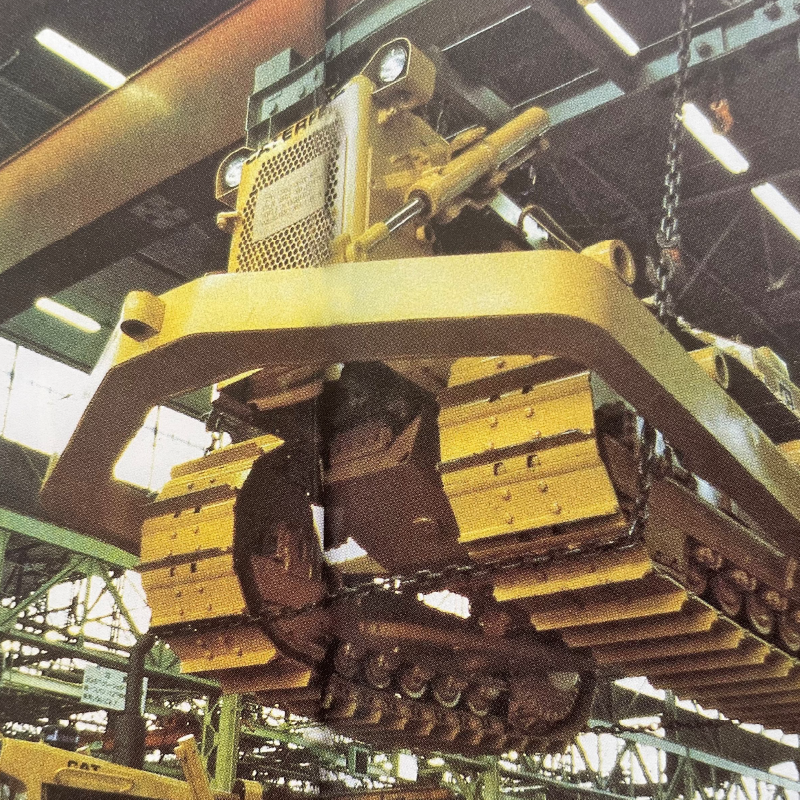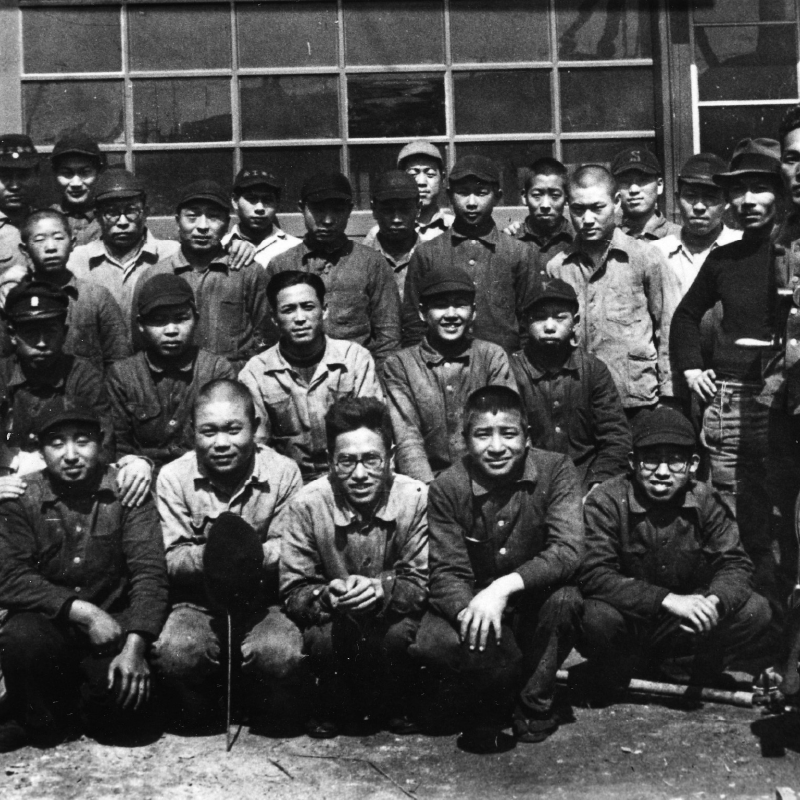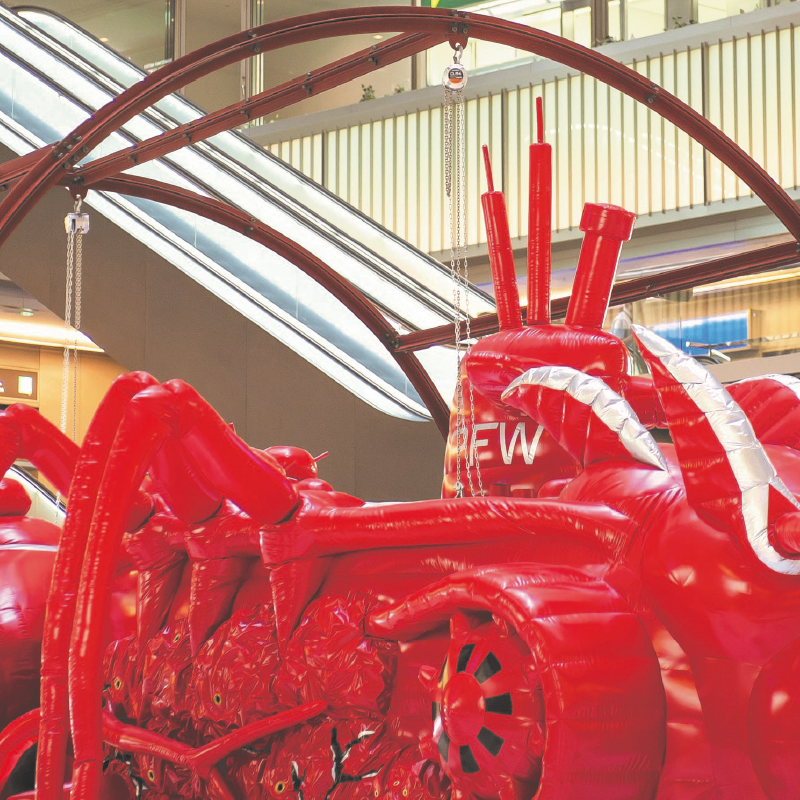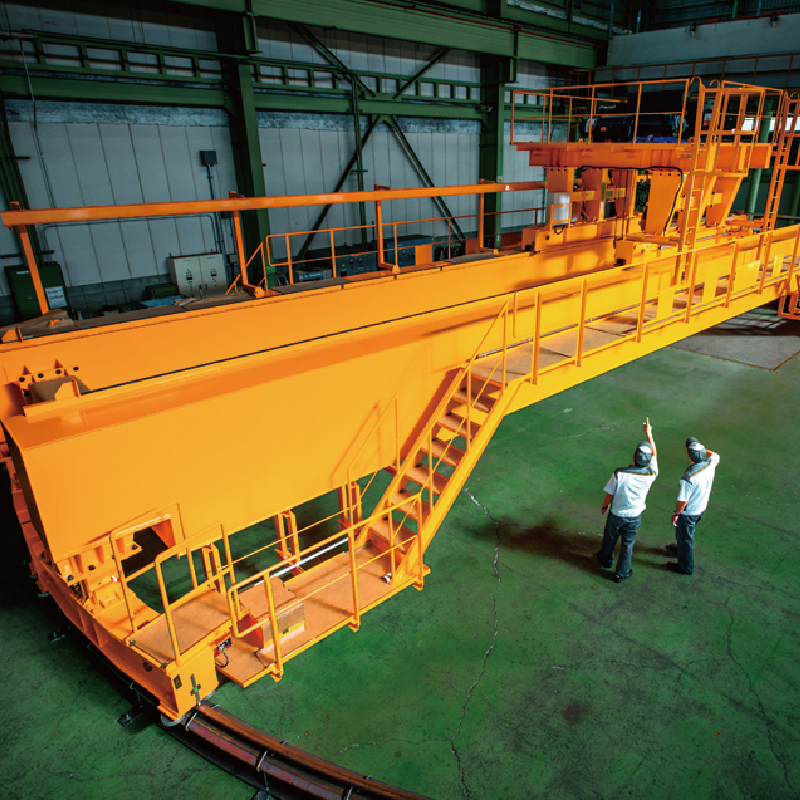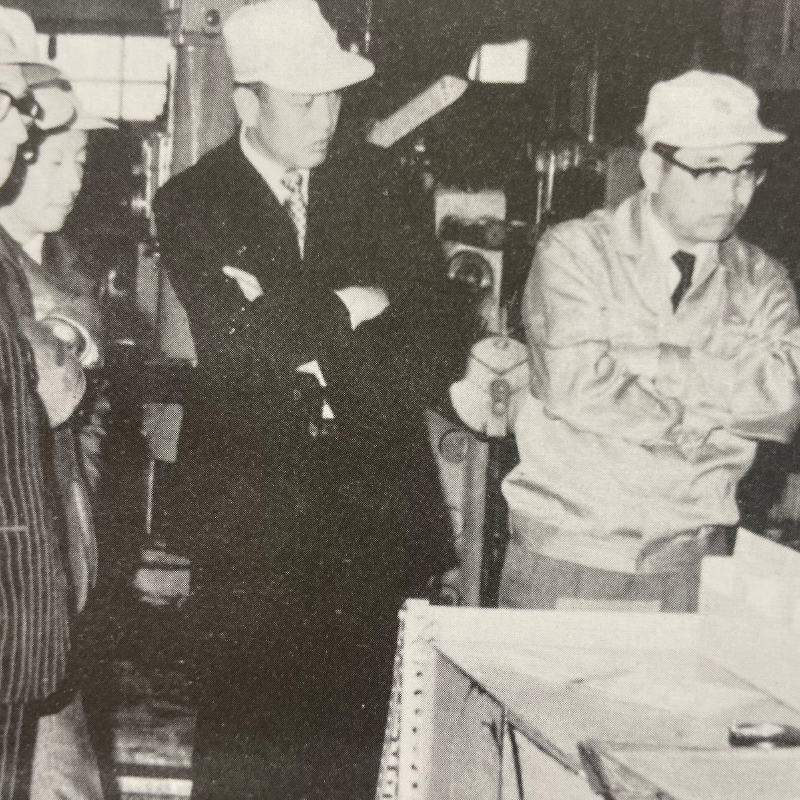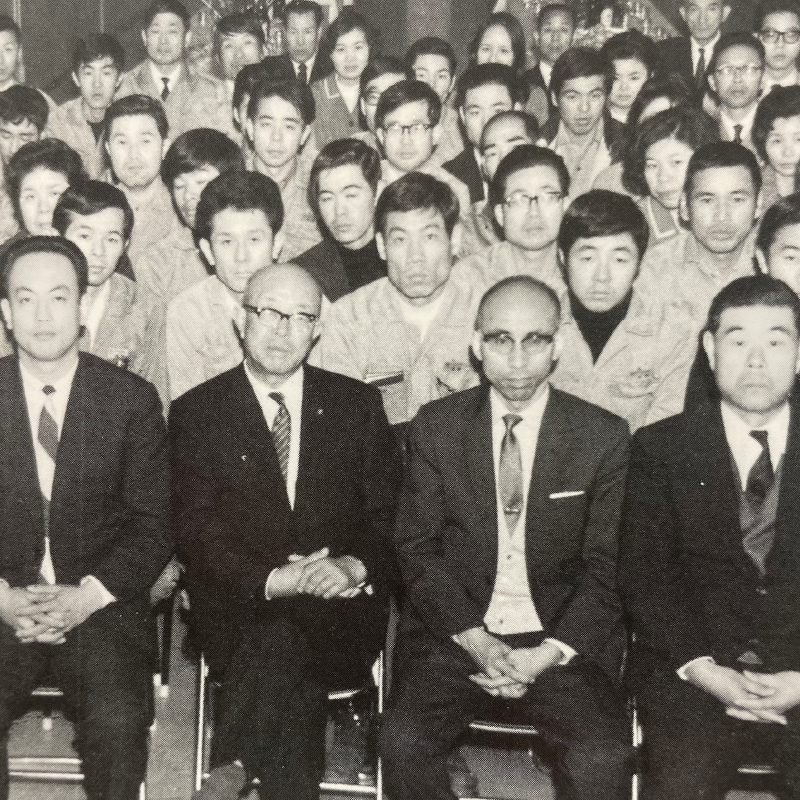KITO at 90
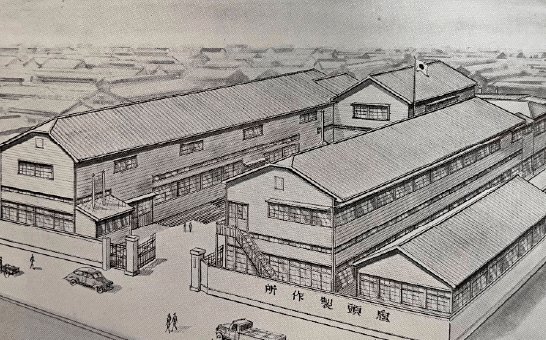
1932
キトーのはじまり
Read More

1934
チェーンブロックとの出会い
Read More
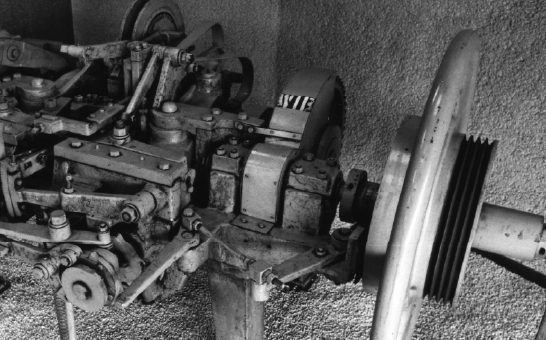
1939
巻上機の生命線
Read More
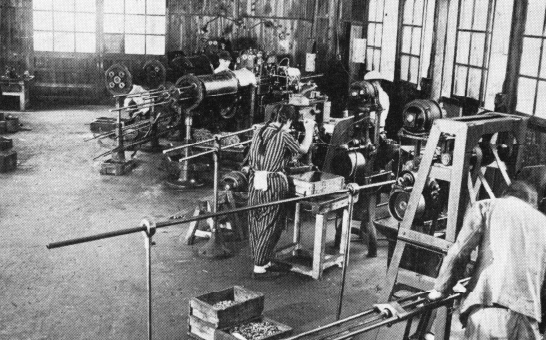
1949
ものづくりの実力を養う
Read More

1969
キトーイエロー
Read More

1949
アフターサービスの先駆け
Read More

1951
米国市場を視察
Read More

2016
オールキトーの逸品
Read More
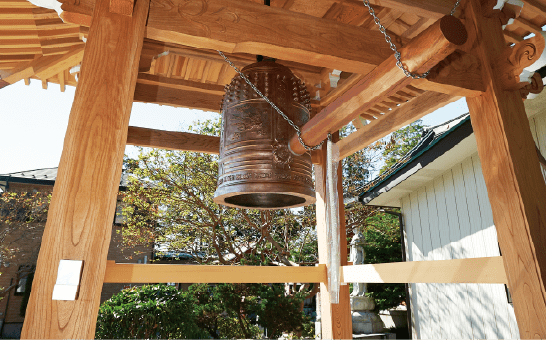
2017
除夜の鐘
Read More
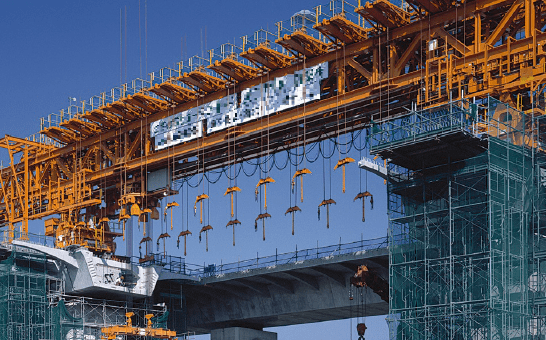
1938
特定セル製品と特定セザル製品
Read More

2017
重量物も人の力でラクラク
Read More

2017
後世に引き継ぐ大切な作業
Read More
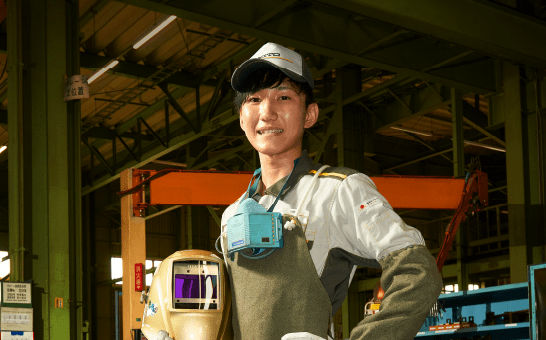
2018
溶接チャンピオン
Read More

1975
愛称はファルコン
Read More
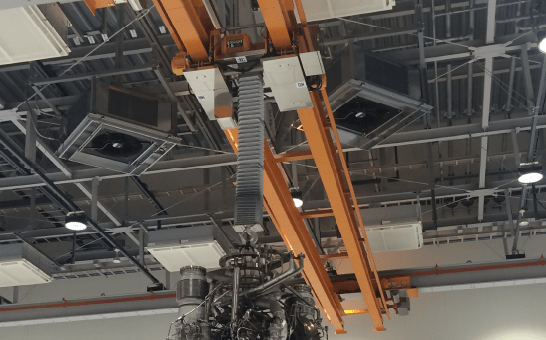
2015
ドラマの小道具
Read More

1959
初代キトーマイティ
Read More
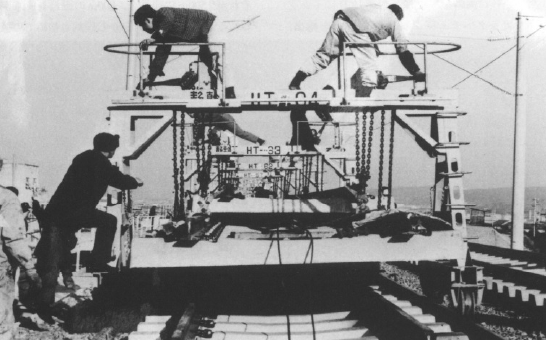
1964
日本の高度成長期を支えるレバーブロック
Read More
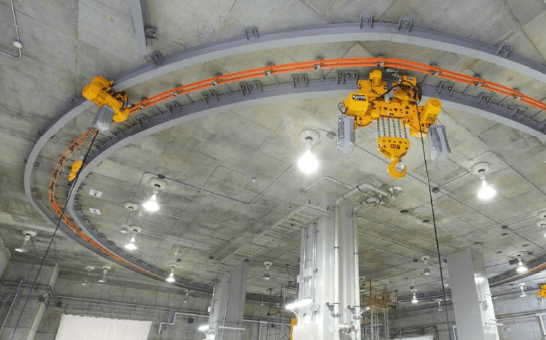
1961
キトー初のクレーン誕生
Read More

2017
誰もが働きやすい企業を目指して
Read More
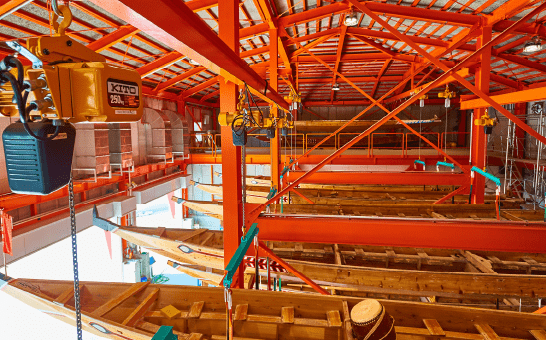
2018
ふるさとへの思いを乗せて
Read More
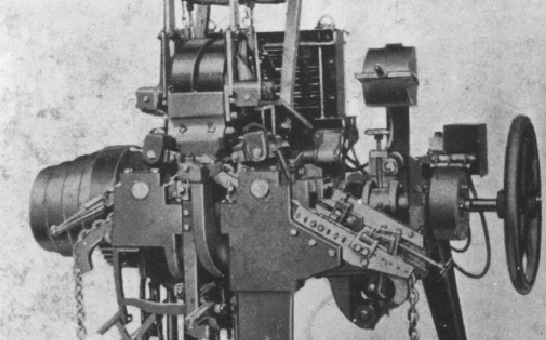
1939
ウェルダーマシン
Read More

2003
グッドデザイン金賞2003
Read More

2012
地上634mのタワー
Read More
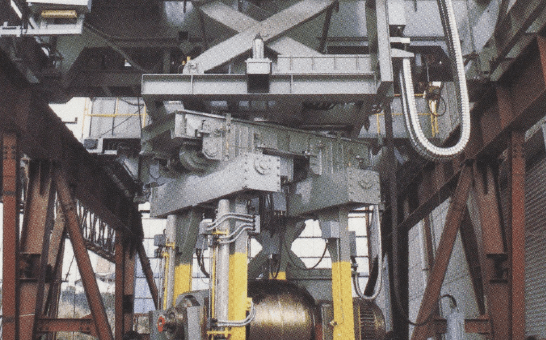
1981
クレーンの未知なる可能性
Read More
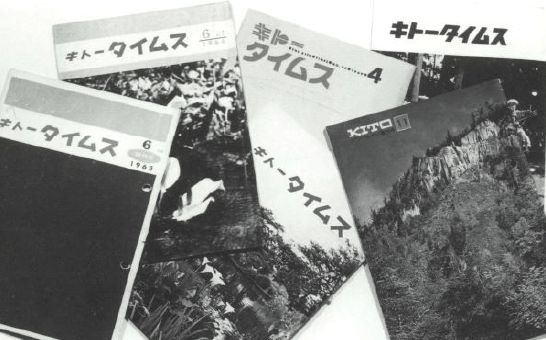
1963
キトータイムス
Read More

2014
復興の地で子どもたちと交流
Read More
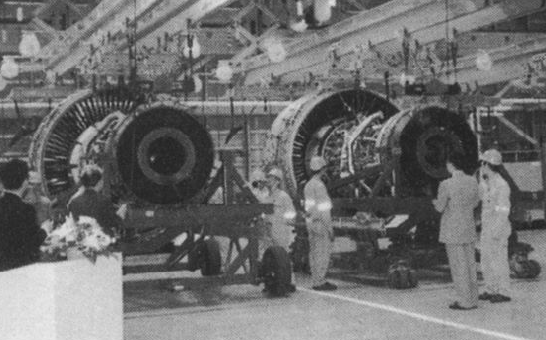
1999
アジア市場への展開加速
Read More
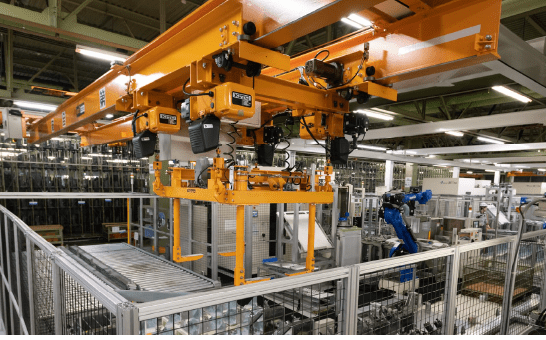
2021
ロボットとクレーンの協働
Read More
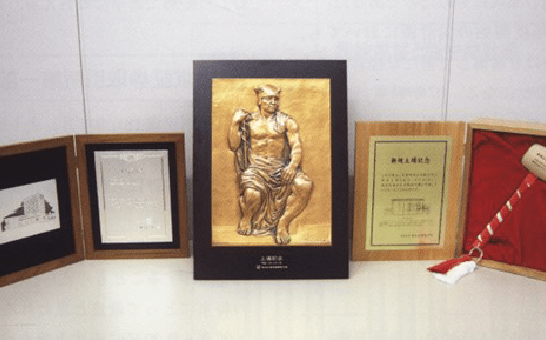
2007
東証第一部上場
Read More
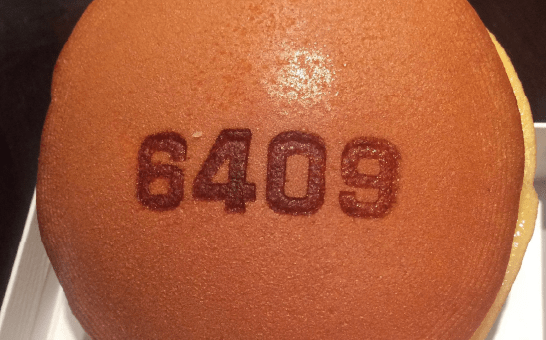
2023
株主の皆さまへ感謝を込めて
Read More

2012
帽子のラインはどんな意味?
Read More

1992
東京本社ビル竣工
Read More
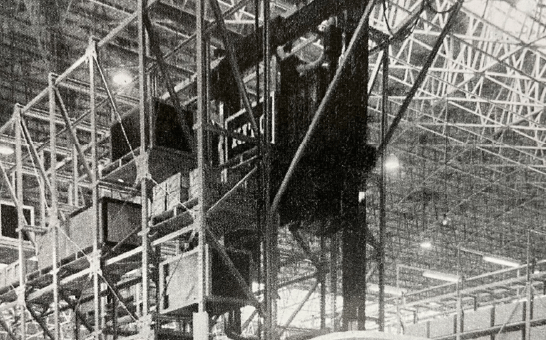
1965
物流の進化!モノリフト誕生
Read More

1945
大漁うなぎは涙の味?
Read More

1939
チェーンブロックの専門工場
Read More

1979
山梨へ全面移転を決断
Read More

1983
移転、800人の葛藤
Read More
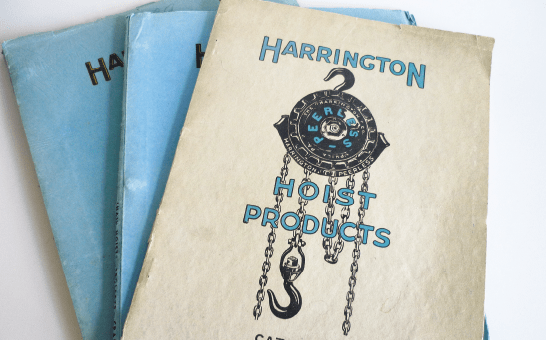
1990
初の海外法人
Read More
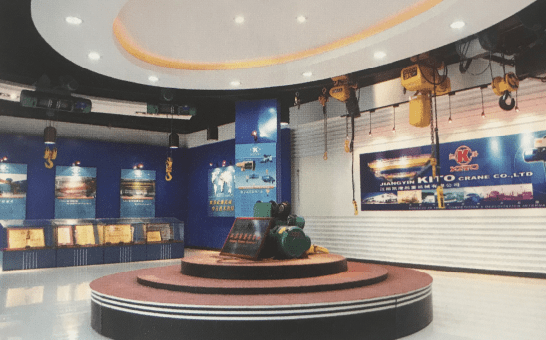
1995
中国事業の始まり
Read More

2006
競合ひしめく欧州へ
Read More
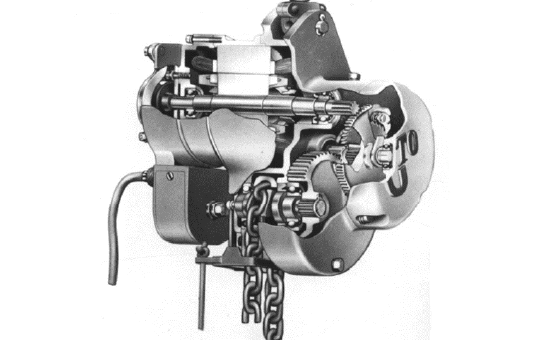
1958
電気チェーンブロック第1号
Read More

2019
タイでホイスト生産
Read More

1954
渋さが光るチェーンブロック
Read More
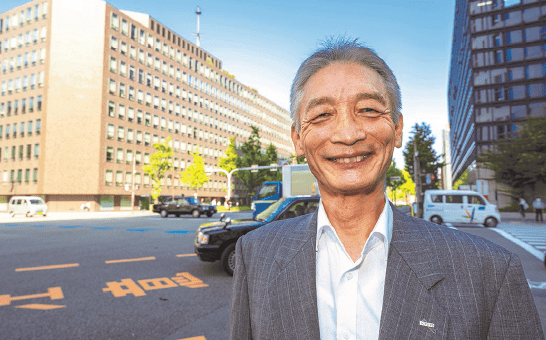
1995
キトー製品を誇りに思う
Read More
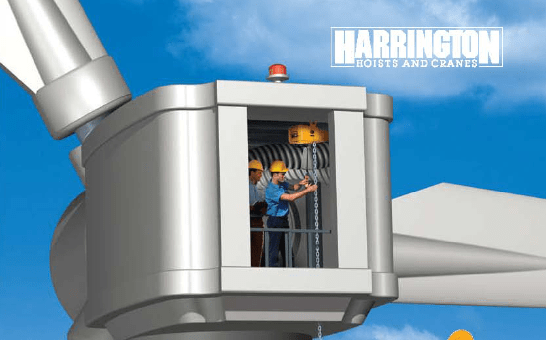
2003
風力発電用チェーンブロック
Read More

2016
お客様の安全な作業環境のために
Read More
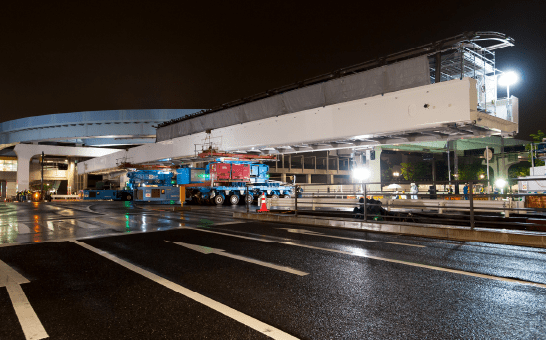
2016
深夜の湾岸エリア
Read More

2011
キトー障がい者雇用の元年
Read More
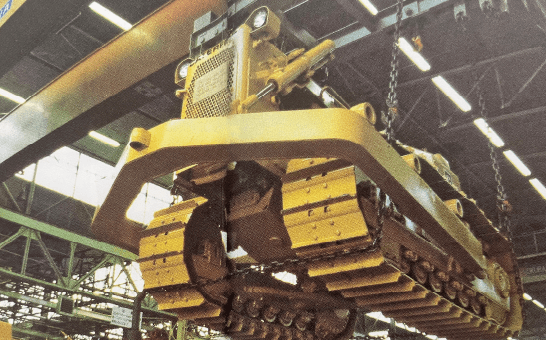
1964
世界最強1,000N/㎟チェーン
Read More

1937
ものづくりは人づくり
Read More

2011
スタイリッシュにキメて!
Read More
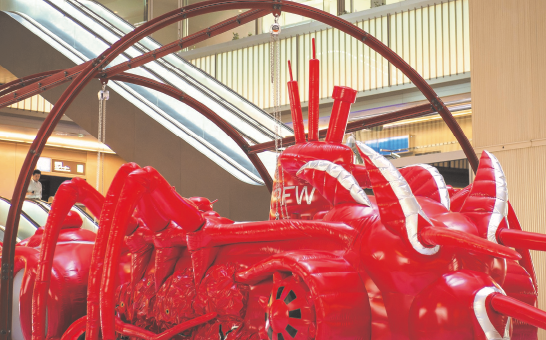
2015
CXが巨大なエビをつり上げる
Read More

2016
30t電動旋回式ダブルガーダクレーン
Read More
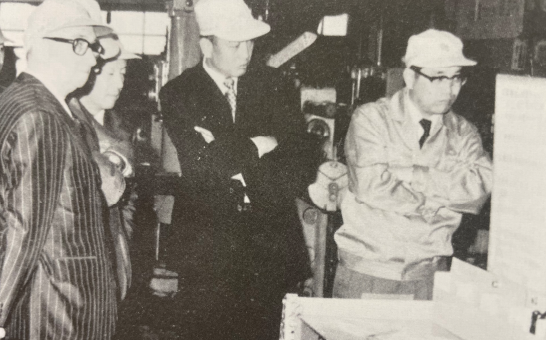
2011
30数年越しのブラジル進出の夢が叶う
Read More
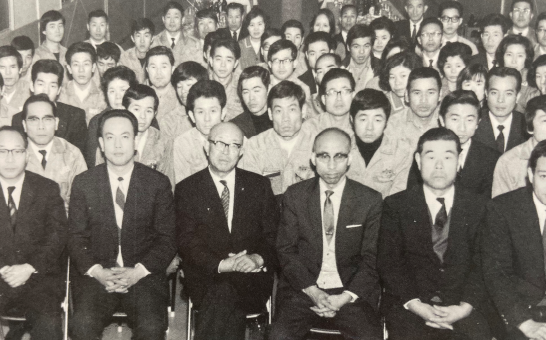
1970
製品・営業・サービスが一体
Read More

1988
大事なことは改善を積み重ねること
Read More

2020
無重力への挑戦
Read More

2022
感動をありがとう!メダリスト来社
Read More
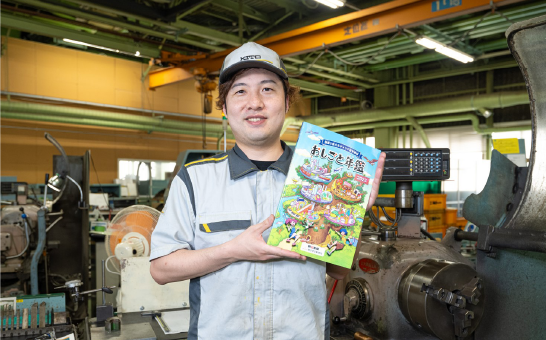
2017
地球でいちばん力持ちの生き物は何?
Read More

2023
第二章のはじまり
Read More